バーチャル商業大学教授のレインディアです。いつもご視聴いただきありがとうございます。

今日は私の研究室に、卒業生がやって来るそうです。

鹿瑠仁:「教授、卒業生の龍爺さんがラウンジに来られていましたよ~。」
レインディア:「わかりました。それでは早速、ラウンジに向かいましょう。」

鹿瑠仁:「こんにちは、龍爺さん。お久しぶりです。」
龍爺:「久しぶりじゃのぅ。先日は債券に関する授業、ありがとう。今日は、長期金融市場について教えて欲しいんじゃが…。」
レインディア:「もちろんですよ。それでは今日も新聞記事を参考にして解説することにしましょう。」

バーミリオン副学長:「そういうことなら、私にお任せください!」
レインディア:「うわー!びっくりした…。副学長、どうしたのですか、急に…!?」
バーミリオン:「久しぶりに、私も学生の相談に乗りたくなりました。」
龍爺:「かたじけないのぅ。今日はよろしくお願いしますぞ。」

バーミリオン:「これは、2003年10月13日の日本経済新聞の朝刊です。この中に、長期金融市場に関する記事がありました。」
レインディア:「『「アジア債券」育成へ金融債(経済教室)』という記事タイトルで、通貨バスケット建て債券などについても解説していますね。」

まず、金融市場は、返済期限によって区分されます。資金の融通を行う場を、金融市場と言います。ここで、金融市場は、短期金融市場と長期金融市場の2つに大別されます。一般的に、資金の融通には返済期限があります。返済期限が1年未満という短い取引を扱うのが、短期金融市場です。一方、返済期限が1年以上の取引を扱うのが、長期金融市場です。まず、短期金融市場は、返済期間が1年未満と短いものを扱う金融市場であり、インターバンク市場とオープン市場があります。インターバンク市場は、金融機関のみが参加可能な金融市場で、金融機関同士で短期間の資金の融通を行います。また、インターバンク市場の中では、コール市場(とりわけ無担保コール翌日物市場)が有名です。一方、オープン市場は、一般企業なども参加可能な金融市場であり、コマーシャルペーパーや国庫短期証券などが取引されます。また、長期金融市場は、返済期間が1年以上のものを扱う金融市場です。長期金融市場では、長期貸付市場において、政府系も含めた金融機関などによる長期融資を中心に行われています。これに対して、証券市場は、株式市場と公社債市場に区分され、株式や債券などが取引されています。

それでは、銀行の融資業務についてみてみましょう。銀行は事前に、借り手の信用度について審査を行います。具体的には、企業に融資する際に、その企業がどのような経営を行い、貸したお金が確実に戻ってくるのかについて審査する必要があります。これをスクリーニングと言います。こうしたスクリーニングをクリアした企業は、借入金額、借入金利、借入期間および返済方法などについて銀行と契約を交わすことになります。実際に融資の実行後、借り手の機会主義的な行動を抑制するために、借り手の行動を監視・監査します。これをモニタリングと言います。ここで、機械主義的行動とは、企業や個人が有利な交渉や取引を進めるために、自分側に有利な情報や相手に不利な情報を相手方に隠したり、積極的に開示しようとはしなかったり、場合によっては裏切ったりするなどの行動を指す言葉です。こうした機械主義的行動を抑制するために、銀行は、モニタリングを通じて、一度限りの取引関係ではなく、長期的に継続する取引関係(長期顧客関係)の構築を図ります。一方、このような長期顧客関係は、将来の安定した資金供給の確保を意味することから、借り手にとってもメリットとなり得るのです。

次に、融資業務の種類についてみてみましょう。融資すなわち貸出は、貸付と手形割引に大別することができます。まず、貸付には、証書貸付、手形貸付、当座貸越などが含まれます。証書貸付とは、貸付先が借用書(正式には金銭消費貸付契約証書)を差し入れて行う融資です。また、手形貸付は、借り手に銀行宛ての約束手形を振り出してもらう融資のことです。さらに、当座貸越は、予め契約をしておくことで、一定限度額まで当座預金の残高を超えても支払いに応じる形式の融資です。その際、企業にとって、残高の不足分は自動的に借入となります。一方、手形割引は、銀行が、企業が持つ約束手形などを、支払期日前に支払期日までの利息を差し引いて買い取る形式の融資です。ここで、約束手形とは、手形の振出人(あるいは交付人)が、支払期日までのその支払いを約束する証書のことです。手形の詳細については、また別の機会に解説することにしましょう。

ホワイトラ副学長:「預金取扱機関の融資業務については、私が解説させて頂きました。バーミリオン副学長、お先に失礼しました。」
バーミリオン:「ホワイトラ副学長、ありがとうございました。それでは、こうした融資業務を踏まえて、長期貸付市場について詳しく解説することにしましょう。」

長期貸付市場は、その名の通り、長期的な融資契約により、資金の融通を行う金融市場です。ここで、融資は、その目的にもとづき、消費性融資と事業性融資に大別されます。まず、消費性融資は、個人のライフステージに応じた資金の融資であり、住宅ローン、マイカーローン、教育ローン、フリーローンなどがあります。一方、事業性融資は、企業が事業を続けるうえで必要な資金の融資であり、運転資金貸出と設備資金貸出に区分されます。ここで、運転資金融資は、原材料の仕入代金や 諸経費の支払いなど、事業の継続に必要な資金を融資する企業向けの融資を指します。すなわち、運転資金融資は、支払われた費用が、現金化されるまでの一時的な資金不足を手当てすることを目的とした融資です。よって、運転資金融資は、売上の回収代金などにより、短期間のうちに返済するため、短期貸付に該当します。

一方、設備資金融資は、工場や店舗、機械・器具など、事業用設備の購入に要する資金を融資するものであり、購入した設備を使用して、生み出される利益の中から返済が行われます。このことから、設備資金融資は、減価償却の耐用年数の範囲内で分割返済するため、長期貸付に該当します。また、家計に対する融資(消費性融資)における長期貸付として、住宅ローン、マイカーローン、教育ローンなどがあります。これらの融資は、いずれも返済期間が1年を超えることから、長期貸付市場に該当します。なお、長期貸付市場は、借手ないし資金使途によって、産業金融市場と消費金融市場に分類されることもあります。ここで、産業金融市場は、主に企業に対して資金を融通する市場であり、消費金融市場は、主に家計に対して資金を融通する市場となります。また、日本で取引される長期金利で代表的なものとして、各年限の国債利回りや金利スワップレートなどがあります。具体的には、長期金利の指標とされるのは、新発10年国債利回りです。ただし、世界的に見ると、米国債が長期債取引の中心で、中でも米国10年債利回りが、世界的な長期金利の指標になっています。

次に、証券市場についてみてみましょう。証券市場とは、株式や債券などの有価証券を取引する市場を指します。また、証券市場には、企業などの発行体が(債券を含む)証券を発行して資金を調達する発行市場としての役割や、証券を売買する流通市場としての役割などがあります。ここで、発行市場と流通市場についても復習してみましょう。(日本を含め世界の)証券市場が果たしている役割として、企業などの発行体が(債券を含む)証券を発行して資金を調達する発行市場としての役割と、証券を売買する流通市場としての役割があります。ここで、発行市場は、プライマリーマーケットとも呼ばれており、企業などの発行体が、証券を投資家に発行する市場となっています。このことから、発行市場は、企業の資金調達手段の1つとして活用されています。なお、発行市場では、予め決まった価格で証券が発行されます。一方、流通市場は、セカンダリーマーケットとも呼ばれており、主として、投資家同士で証券の売買が行われます。そのため、価格はその時々で異なり、時価で売買されることになります。なお、多くの場合、証券取引所で価格が決定されます。こうした証券市場は、株式市場と公社債市場に区分され、それぞれのマーケットにおいて、株式や債券などが取引されています。

また、株式市場の目的として、企業の観点からは事業拡大のための資金調達という目的が、投資家の観点からは透明性のある価格での投資家による株式売買・流動性の向上という目的が挙げられます。以来、これらの本来の機能は拡張を続け、現在、公開株式市場は企業や投資家に、より多くの恩恵をもたらしています。また、株式市場において、新規公開株式(IPO:Initial Public Offering)は、発行市場で取り扱われます。ここで、IPOとは、企業による事業の資金調達を行う一手段として上場し、その際の株式公開を指します。その一方で、一般的には、流通市場のことを株式市場と呼びます。例えば、日常的に目にする株価や株価指数などは、流通市場で取引されている価格となります。また、流通市場は、取引する内容により、現物市場とデリバティブ市場に分けられます。ここで、現物市場では、上場企業の株式の売買が行われており、日本国内における上場株式の売買は、東京、名古屋、福岡、札幌の4か所の証券取引所で行われています。一方、デリバティブ市場では、金融派生商品の取引が大阪取引所で行われています。なお、デリバティブ取引やデリバティブ市場の詳細については、また別の機会に解説することにしましょう。

次に、債券市場についてみてみましょう。債券市場で取引される主な債券は、公共債および社債となります。一般的に、債券市場は、公社債市場とも呼ばれており、株式市場と共に証券市場を構成しています。ただし、債券市場において、その売買の多くは、店頭取引(相対取引)で行われています。ここで、店頭取引(OTC:Over The Counter)とは、証券取引所を通さずに、証券会社等と投資家の間で売買を行う取引を指します。日本において、債券では、99%以上が店頭取引であり、証券会社だけでなく銀行などの金融機関でも一部売買されています。また、店頭取引(相対取引)では、売り手と買い手が当事者同士で、価格や取引数量を決めて売買が行われます。こうした店頭取引が中心となる債券市場では、国債・地方債・ 社債などの債券の取引が行われます。ここで、国が発行する国債、地方公共団体が発行する地方債をまとめて公共債と呼びます。なお、国内市場では、主に日本で発行される債券(日本国債など)が取り扱われます。一方、海外市場では、主に海外で発行される債券(外国債)が取り扱われます。また、債券の先物取引は、大阪取引所に上場されています。なお、先物取引については、また別の機会に解説することにしましょう。

また、債券市場において、参加者の多くは、債券トレーダーや機関投資家などの運用のプロとなっています。ここで、債券トレーダーとは、店頭市場で債券の売買を仲介する役割を担うプレーヤーであり、売買額の差が収益とされます。なお、個人投資家も参加可能であるものの、株式市場に比べると存在感は低くなっています。ところで、債券市場では、各国の金融政策、需給バランス、将来の金利見通し等により、債券価格が変動します。ここで、需給バランスとは、債券や株式の価格は、需要と供給によって決まることを指します。証券市場において、買いたい人が多ければ価格が上がり、買いたい人が少なければ価格が下がります。よって、これらの要因に応じて、債券市場での取引にも波が生じます。また、世界全体でみると、株式市場よりも債券市場の方が規模が大きい傾向があります。とりわけ、米国市場が世界最大であり、そこでは、米ドル建ての債券が世界で最も多く取引されています。

今回の授業を締め括るにあたり、最初に紹介した新聞記事について解説することにしましょう。今回の新聞記事の投稿現在において、アジア債券市場の発展には、円資金が市場を循環する枠組みの構築が不可欠でした。このことから、域内外の間の大規模な資本移動を抑制しつつこの枠組みを定着させるには、まず民間銀行が発行する金融債市場を、複数の主要通貨に連動するバスケット通貨建てで育成することが効果的でした。そのため、新市場創設の動きが加速しました。具体的には、2003年の初めから高まったアジア債券市場創設の機運は、同年8月のASEANプラス3財務相会合、同年9月のAPEC財務相会議を経て、劇的な前進を見せました。そこでは、ASEAN+3各国を議長国とするワーキンググループが組織され、発行市場での信用保証や格付け、市場育成技術支援など実務レベルでの検討も始まりました。従来のアジア地域金融協力は、危機防止策が中心でした。1998年以降、日本を中心とする東アジア諸国はASEANサーベイランスプロセスなどの資本フロー監視システムの構築、チェンマイ・イニシアチブ(複数の二国間通貨交換協定)など金融セーフティーネットの整備に邁進してきました。このことから、今回の新市場育成の取り組みは、金融面で東アジア諸国が更なる成長を達成するための基盤整備であり、東アジアの新金融秩序が危機防止型から高機能・高利便性型システムを模索する段階に入ったことを象徴しました。

しかし、当時世界第2位の経済大国である日本でさえ、個人貯蓄の7割が預貯金である事実からみても、新債券市場創設が即、東アジア域内の個人貯蓄吸収に直結しないことは容易に理解できました。また当時、内部資金と一年未満の短期借り入れが主たる資金調達手段である東アジアの地場企業にとって、債券発行のニーズがどの程度存在するかも懐疑的でした。更に、新市場創設は日本の投資家にとってそもそもどのようなメリットが将来期待できるのか、また、これまで政府が進めてきた円の国際化、将来のアジア域内通貨制度とどのようにかかわっていくべきであるのかという点を含め、論点を今一度整理する必要がありました。もともと、アジアにおける債券市場の育成は、1984年以降、世界銀行およびアジア開発銀行がドラゴン債(日本を除くアジアの複数の市場で発行される債券)の発行を通じた育成を試み、同時に域内共通決済システムの構築も長年切望されてきました。しかしながら、ドラゴン債は米ドル建てであることから、機関投資家がユーロ債、ヤンキー債(米国市場のドル建て債)をよりも選好することが多く、市場間競争で常に苦戦を強いられてきました。

また、1990年代後半には「アジアクリア」と称される共通決済システムの構築を望む声も一部であがりましたが、特に法制度面での国際的調和の困難性から、具体的な設立の動きへは至りませんでした。今回の新債券市場は、当初案では米ドル建てを前提としていましたが、現段階では各国通貨建て債券発行を目指していることから、ドラゴン債が直面した市場間競争の問題からは免れました。その半面として生じる課題は、交換性が低い各国自国通貨建て債券に、どのように国内外投資家にとって魅力的な商品価値を付与するかという点でした。実際に、国際決済銀行(BIS)による2002年の報告では、直近3年間にアジアの発行体が発行した外貨建て債券の45%前後は、アジア域内の投資家に購入されていました。しかし、そのほとんどは域内に拠点を持つ米欧系投資銀行を中心とするシンジケート団により引き受けられていました。逆に言えば、地場金融機関での巨額の引き受けは、彼らの総資産規模から見て難しいことを意味しました。

その一方で、新債券市場の育成にあたっては、当初は準備段階として自国通貨建て債券を各国公的セクター並びに国際開発機関などが発行し、調達資金を企業向け融資の原資とするなどの方向性が検討されていました。この場合、公的機関が発行した債券発行残高が増大するにつれて、各国で適正なイールドカーブ(利回り曲線)が描かれることが期待されましたが、交換性が低い自国通貨建てであるがゆえに、主たる購入者は国内機関投資家に限定される可能性がありました。また、市場で消化された債券をどのように家計部門へ販売し、個人貯蓄を吸収するのかという販売チャネルの問題もありました。更に、発行体の情報生産を行う格付け機関に、各国格付け機関を採用する是非についても考えなければなりませんでした。これは、各国地場格付け機関の格付け実績は普通債で企業数30社前後にとどまっており、債券発行頻度が高い一部の大企業に集中していたためでした。

こうしたことから、東アジア企業の債券発行需要については、現時点では北東アジア諸国、シンガポールを除き、ほとんどその需要はないと解釈すべきでした。この根拠として、企業ミクロデータを用いた今回の記事における分析において、東アジアではいずれの国においても企業の設備投資資金は、内部資金ないしはグループ内企業間信用に依存しており、韓国、シンガポールなど一部の地域を除き不足分は、一年未満の銀行借入で賄われていました。このため、債券発行のニーズは、もう1つの外部資金である銀行借入よりも調達コストが安価でなければ、企業にとってメリットは小さい状況でした。その一方で、新債券市場の創設が具体的な実務レベルの議論にまで進展したことは大きな前進でありましたが、債券の購入者や地場企業の資金調達行動などの問題を踏まえると、道のりは険しいことは明らかでした。

新債券市場の育成は、資本の動きを域内で完結させ、大規模な資本が域内外間を移動することを抑止すること、および各国国内での企業のドル建て調達率が依然として大きいことから、通貨下落による負債価値の変動を回避することが目的とされていました。ゆえに、この2つの目的を同時に達成するには、米ドルに対して変動し、かつ日本円に対して変動が小さい通貨バスケット建て債券が最も有効ではないかと考えられました。こうしたバスケット通貨建て債券は、過去の研究プロジェクトにおける将来のアジア通貨システムの方向性とも合致しており、将来、アジア域内の通貨制度が債券市場の主導によりバンド(一定幅の)バスケット制へ収斂すれば、東アジア各国企業が晒される為替リスクも極小化されることが期待されました。また、先進国通貨を含むバスケット通貨建て債券が発行されれば、域内有力機関投資家の参加を促し、日本や米国などの格付け機関による情報生産も行われ易いとも考えられました。

しかしながら、東アジア域内の資本市場の現状を考慮すると、急速な直接金融化はやはり実現可能性が低いと予測されました。また、この新債券市場の育成過程において、長期金融債を保証付きバスケット通貨建てで発行することが、効率的貯蓄吸収に寄与するとも考えられました。実際に、日本、韓国、台湾という民間銀行による長期ローンの提供が定着している国・地域では、いずれも1950年代から1970年代にかけて長期信用銀行法が制定され、金融債の発行によりバランスシート上の負債と資産の長期化が進行しました。その際、金融機関の債券が市場の育成過程で優れている理由として、金融機関は一般事業会社に比べ総資産規模が大きく、また知名度が高い点が挙げられました。また、広範な支店網を通じてリテール市場と接点持つため、個人貯蓄を吸収し易い状況にありました。このように、短期借り入れに依存する現在の東アジアの企業金融の特徴を踏まえ、販売チャネル面で最も優位にある銀行店舗を利用した長期金融債の発行が、地域の貯蓄を吸収し、企業の借入期間長期化を促し、将来的には負債の為替リスクを除去することに最も効果的であると考えられました。

なお、東アジア域内企業の債券発行需要に関しては、直近で長期資金需要がないことは、決して長期資金調達市場の存在意義を否定するものではありませんでした。例えば、東アジアでの域内分業体制構築を進める日本企業では近年、研究開発(R&D)拠点も各国現地へ移行する動きが見られ、将来にはASEAN企業も、高付加価値、技術集約型輸出製品の生産へ移行することは確実視されていました。とりわけ、設備投資に比べ短期的な成果が現れにくいR&D投資では、企業は常に借入制約と直面 することから、長期金融市場の存在は不可欠なものとなります。最後に、バスケット通貨建て債券は日本から東アジアへの資金還流を促す効果も有します。これは、当時、4.7兆円存在する日本の個人外貨預金よりも、為替リスクおよび信用リスクの2つの面で優れているためです。

バーミリオン:「いかがでしたか?長期金融市場は、金融市場のうち取引の期間が1年以上の比較的長期の資金を融通する市場であり、その代表が証券市場(資本市場)なんですよ。」
龍爺:「よく分かりましたぞ。バーミリオン殿、今日は有り難うございました。」

バーミリオン:「今日は、私の研究室で授業をすることができて楽しかったです。また、私の研究室で授業しましょうね。」
レインディア:「バーミリオン先生、とても勉強になりました。今日はありがとうございました。」

レインディア:「ふぅ~、久しぶりにバーミリオン副学長のお部屋に伺いました…。」
鹿瑠仁:「レインディア教授も久しぶりなのですか!? おしゃれな部屋でしたが、副学長のオーラが漂っていましたよね…。」
レインディア:「バーミリオン副学長のお話はまた聞きたいけど、あの部屋にまた行くのはちょっと…💦」
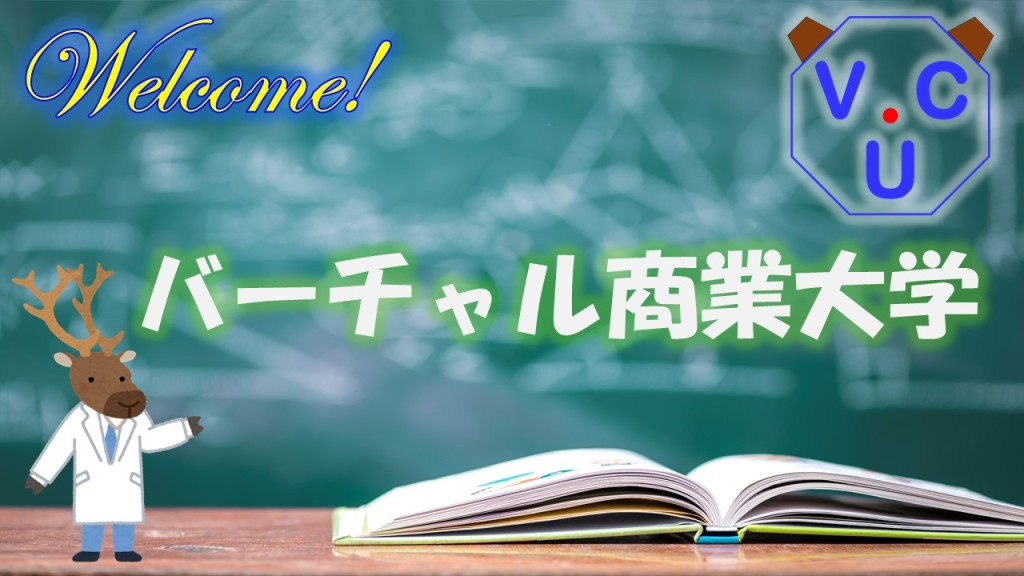
バーチャル商業大学では、毎回、個性的な学生から寄せられる質問について、レインディア教授と鹿瑠仁(しかるに)助手が懇切丁寧に解説します。
大学の講義って社会で役に立つの!? 商学部・経営学部・経済学部の授業を知りたい!リカレント教育を受けたいけど今更大学に行けない!などなど…。
そんな悩みをお持ちの方に、日頃の生活でも役立つ商学・経済学・ビジネスの小ネタなどを配信していきます!
金融・経済・ビジネス情報をアカデミックに理解したい方、大学のビジネス関係の授業でお困りの方は、ぜひブックマークへの登録などをお願いします!
最後までお読み下さりありがとうございました。また次回の授業でお会いしましょう。